住まいのコラム
【第133回】【2024年度】住宅税制の変更点まとめ!役立つ制度や注意点も解説
2024.06.28
注文住宅を建てたり、住宅を購入したりする際に気になるのが費用面です。マイホームは決して安い買い物ではないため、「できるだけお得に建てたい」「金銭的な負担を軽減できる制度を利用したい」と考える方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、2024年度に活用できる住宅税制について解説します。「一生に一度の買い物」ともいわれるマイホーム購入で損をしないために、住宅税制の変更点や活用する際の注意点について知っておきましょう。

<INDEX>
- 毎年改正される住宅税制について
- 住宅ローン減税の変更点
- 贈与税の非課税措置の変更点
- 既存住宅のリフォームの所得税に関する変更点
- 子育てエコホーム支援事業について
- その他の税制特例
- 【2024年】住宅税制を活用する際の注意点
- まとめ
毎年改正される住宅税制について

住宅を購入する際は、税制を上手に活用することで金銭的な負担を減らすことが可能です。税制は生活に大きく関わるものであり、経済状況の変化に対応したり、負担の公平性を確保したりするために、継続的な見直しが行われています。住宅関連の税制も毎年変更されるため、最新の情報をチェックすることが重要です。
2024年度においては、2023年12月22日に「2024年度(令和6年度)税制改正の大綱」が閣議決定されました。この税制大綱には、子育て世帯への支援強化の必要性や急激な住宅価格の上昇などを踏まえ、住宅ローン減税の制度変更などが盛り込まれています。
住宅ローン減税の変更点

まずは、住宅ローンを利用する際に必ず知っておきたい「住宅ローン減税」の変更点について解説します。住宅ローン減税は金額が大きく、数百万円の節約につながることも珍しくありません。制度を把握して上手に活用しましょう。
住宅ローン減税とは
「住宅ローン減税」とは、住宅ローンの年末残高のうち0.7%を13年間(中古住宅の場合は原則として10年間)にわたって所得税から控除する制度です。所得税から控除しきれない場合は、住民税から控除されます。控除の対象となる年末残高の借入限度額は、住宅の性能によって異なり、「長期優良住宅」や「低炭素住宅」といった高性能な住宅のほうがより高額です。
ただし、住宅ローンを借りているすべての方が住宅ローン減税の対象となるわけではありません。利用するには「建物の床面積が原則50㎡以上」「世帯×申告する個人の合計所得が2,000万円以下」「住宅ローンの年数が10年以上」といった要件を満たす必要があります。
【住宅ローン減税】2024年度の変更点
上段では2023年以前の要件を記載しましたが、2024年以降新築住宅に入居する場合、すべての住宅において借入限度額が引き下げられ、最大控除額も下がりました。また、2024・2025年に入居予定の新築住宅について申請する場合は、省エネ基準を満たしていることも必須となっています。ただし、2024年度の税制改正では、子育て世帯(19歳未満の子どもがいる世帯)や若者夫婦世帯(夫婦のどちらかが40歳未満の世帯)が2024年に入居する場合には、一定の上乗せ措置を講ずることで2022・2023年入居の場合の水準と同水準にすることが盛り込まれました。
上乗せ措置の金額は、長期優良住宅と低炭素住宅が500万円、ZEH水準省エネ住宅と省エネ基準適合住宅が1,000万円です。
つまり、子育て世帯・若者夫婦世帯のみ、控除の対象にできる借入限度額が500万~1,000万円高くなるため、その他の世帯と比較すると有利になっています。
入居年度が異なる場合の借入限度額の引き下げ措置は以下のとおりです。
| 2022・2023年入居 | 2024・2025年入居※ | |
|---|---|---|
| 長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯は5,000万円に変更) |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯は4,500万円に変更) |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 (子育て世帯・若者夫婦世帯は4,000万円に変更) |
| その他の住宅 | 3,000万円 | 0円 (2023年までに新築の建築確認:2,000万円) |
※2025年入居については、2025年度税制改正にて2024年入居と同様の方向性で検討してる。
また床面積に関しては、前節で「建物を床面積が原則50㎡以上」と記載しましたが、新築住宅に限り「2024年12月31日までに建築確認を受ける」「世帯×申告する個人の合計所得が1,000万円以下」という要件を満たすことにより、「床面積40㎡以上」という緩和措置が取られています。
贈与税の非課税措置の変更点

住宅を建てたり購入したりする際に、親族から金銭的な援助を受けるケースがあります。「住宅資金として受け取ったお金は、贈与税がかからない」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。ここでは、住宅購入における贈与税の非課税措置がどのように変わったのかを解説します。
贈与税の非課税措置とは
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」とは、父母や祖父母(直系尊属)などから住宅資金の援助を受ける場合、一定額までであれば贈与税を非課税にする制度のことです。
個人から年間110万円を超える金銭や財産を譲り受けたとき、通常であれば贈与税が発生します。しかし、親や祖父母から住宅資金として受け取る場合に限り、「良質な住宅」であれば1,000万円、「それ以外の住宅」は500万円まで非課税となります。
【贈与税の非課税措置】2024年度の変更点
贈与税の非課税措置は、当初2023年12月31日までと決められていましたが、3年間延長され2026年12月31日まで継続されることになりました。
一方で、非課税額が1,000万円となる「良質な住宅」の基準は厳しくなり、「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」を満たす必要があります。ただし、2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅、または2024年6月30日までに建築された住宅については、「断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上」という従来の基準が適用されます。
既存住宅のリフォームの所得税に関する変更点

既存住宅のリフォームを行う場合も、所得税の控除を受けられるケースがあります。控除を受けるために必要な条件や、2024年度の変更点をチェックしておきましょう。
既存住宅のリフォームの所得税とは
既存住宅のリフォームに対する所得税の特例措置を活用すると、リフォームにかかった工事費用の10%が所得税から控除されます。
ただし、すべてのリフォームが対象となるわけではありません。控除を受けられるのは、既存住宅に対して「耐震」「バリアフリー」「省エネ」「三世代同居」「長期優良住宅化」のいずれかを目的としたリフォームを行う場合です。
【既存住宅のリフォームの所得税】2024年度の変更点
2024年度の変更では、当初は2023年12月31日までだった適用期限が2025年12月31日までとなり、2年間延長されています。さらに、従来のリフォーム条件に加え、子育て世帯や若者夫婦世帯による「子育て」に対応したリフォームも対象となりました。子育てのためのリフォームで控除される金額は、最大25万円です。こちらの期限は2024年12月31日までとなっています。
子育てエコホーム支援事業について

2024年度の税制改正の背景には、少子化対策や子育て世帯への支援強化があります。ここでは、子育て世帯がマイホームを建築または購入する際などに活用できる「子育てエコホーム支援事業」について解説します。
子育てエコホーム支援事業とは
「子育てエコホーム支援事業」とは、注文住宅を建てたり建売住宅を購入したりする子育て世帯や若者夫婦世帯に対し、補助金を支給する国の事業です。既存住宅をリフォームする場合も対象となります。
2023年に実施された「こどもエコすまい支援事業」が予算上限に達し、早期に受け付けが終了したことを受け、2023年度と2024年度で合わせて2,500億円という大規模な予算が組まれました。
対象要件・補助金額
対象要件や補助金額については以下の表のとおりです。リフォームは工事内容に応じて上限が設定されていますが、子育て世帯や若者夫婦世帯がリフォームを行う場合は、上限60万円に引き上げられます。補助を受けるのに必須の工事と、必須の工事と同時に行うことで対象となる工事があるため、注意しておきましょう。
| 注文住宅の新築 新築分譲住宅の購入 |
リフォーム | |
|---|---|---|
| 対象者 | 子育て世帯もしくは若者夫婦世帯のみ | 工事を発注したすべての方 |
| 補助金額 |
|
|
| 対象住宅・リフォーム | 床面積が50㎡以上240㎡以下の住戸 | 開口部の断熱改修、エコ住宅設備の設置など |
※1 住宅が市街化調整区域かつ土砂災害警戒区域または浸水想定区域に該当する場合の補助金額
※2 既存住宅購入を伴う場合(リフォームのみだと上限30万円/戸)
その他の税制特例

上記で紹介したもの以外にも住宅税制はさまざまな特例措置があり、期間が延長されたものがあります。以下のような特例も併せて覚えておきましょう。
- 印紙税の軽減措置:建物建築工事請負契約書や土地建物売買契約書などに必要な印紙税を軽減(2027年3月31日まで)
- 固定資産税の減額措置:新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンションは5年間)にわたり2分の1に減額(2026年3月31日まで)
- 登録免許税の軽減措置:登録免許税の税率の軽減(土地の売買による所有権の移転登記は2026年3月31日まで、住宅所有権の保存登記および住宅取得資金の貸付け等にかかる抵当権の設定登記は2027年3月31日まで)
- 所得税の特別控除:認定住宅等の新築にかかる費用の10%(最大65万円まで)を所得税から控除
- 特定の居住用財産の買換え特例:マイホームの買換えで利益が出たときの課税の繰り延べ(2025年12月31日まで)
- 認定長期優良住宅の特例措置:認定長期優良住宅を取得した際の所得税・登録免許税・不動産取得税・固定資産税を一般住宅特例より軽減、控除額を増額(所得税:2025年12月31日まで、登録免許税:2027年3月31日まで、税率が所有権保存登記0.1%など引き下げ、不動産取得税:2026年3月31日まで、控除額が1,300万円に増額、固定資産税:2026年3月31日まで、適用期間が5年間(マンション等は7年間)まで延長)
【2024年】住宅税制を活用する際の注意点

お得な制度を最大限に活用するには、まず制度について調べ、内容や注意点を把握しておくことが大切です。以下では、住宅税制を活用する際の注意点について解説します。
自治体ごとの補助制度も確認する
国が実施する住宅税制や支援事業だけでなく、各自治体が独自に実施する補助金制度についてもチェックしておきましょう。自治体の制度は国の制度と併用できるものが多く、上手に使うことで金銭的な負担を軽減できます。
予算枠が決まっているため早めに申請する
「子育てエコホーム支援事業」などは、予算があらかじめ決まっています。申請期間内であっても予算に達すると受付が終了してしまうため、注意が必要です。特に制度が手厚いものであればあるほど、利用者も多くなります。住宅の新築や購入を検討する際は、税制や補助金制度も確認しつつ、できる限り早めに準備をして申請しましょう。
確定申告する
住宅ローン減税を受けるには、マイホームに入居した翌年に確定申告をする必要があります。自動的に控除されるわけではないため、忘れないように手続きを済ませましょう。会社員などの勤め人であれば、確定申告を行うのは初年度のみで良く、2年目以降は勤務先にローンの残高証明書を提出すれば、年末調整のみで手続きが可能です。
まとめ
2024年の住宅税制を確認してお得に家づくりを進めよう
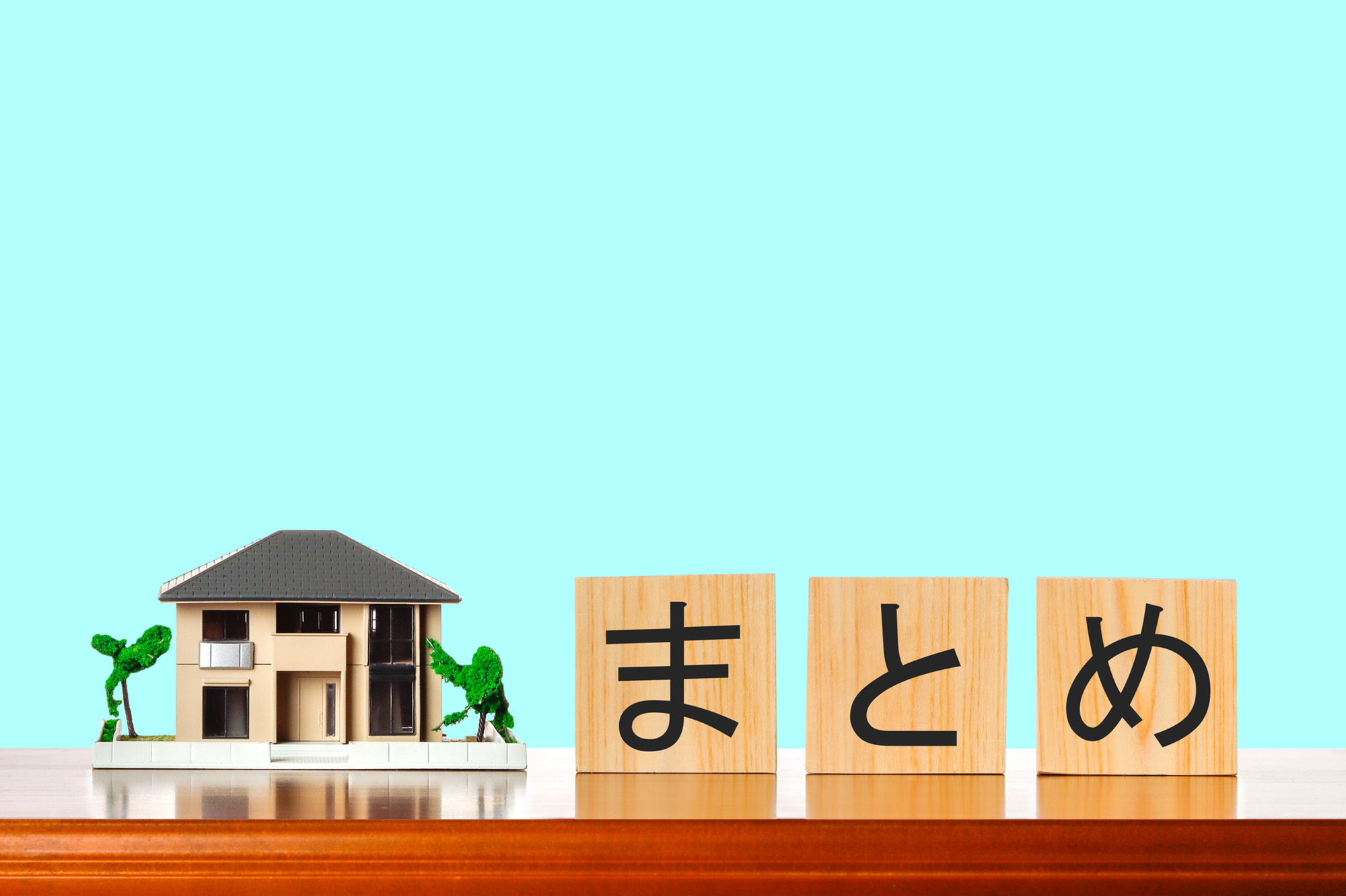
住宅税制も含め、毎年さまざまな税制改正が行われています。2024年度では、リフォームによる所得税の減税要件に子育てに対応したリフォームが追加されるなど、手厚くなった部分も見られました。
お得な制度を活用しつつ注文住宅を建てるには、国や自治体の制度をチェックしつつ、住宅展示場に足を運んで家づくりのプロに話を聞いてみましょう。「家サイト」では、全国にある住宅展示場の検索や見学申し込みが可能です。理想的なマイホームづくりのために、ぜひお役立てください。
住宅展示場・モデルハウスの検索・予約はこちらから
監修・情報提供:馬場 愛莉(2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級))
Ⓒ2024 Trail.inc
本記事はTrail(株)が記事提供しています。
本記事に掲載しているテキスト及び画像の無断転載を禁じます。






.png)
